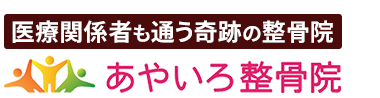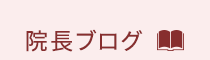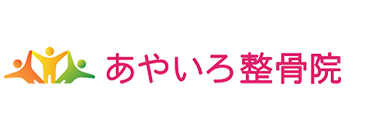みなさん、こんにちは!
頭痛めまい専門 群馬県 前橋市 あやいろ整骨院 スタッフのカズヤスです。
先週の土曜日に操体法の練習会に参加してきました!
会場は、東京都足立区の下井接骨院。
午前は、理学操体練習会。
午後は、多次元操体法練習会。
…ということで、なんと午前、午後のダブルヘッダーでした!
午前の部:理学操体練習会
この理学操体練習会は、理学操体の創始者である、ひふみ健康院 の 加藤 廣直 先生 が開催された、技術習得セミナーのフォローアップ勉強会です。
セミナーに参加した方で、さらにレベルアップをしたいという熱心な先生が集まります。

【40肩、50肩へのアプローチを検証中】
「理学」と名のつくだけあって、理論的な学びの多い練習会です。
今回は「症状の原因の探り方やその対処方法」について学んできました。
「膝が痛い」「肩が動きづらい」「腰に重さを感じる」など、普段の施術の場面では、いろいろな症状の方々がいらっしゃいます。
そして、そんな方々への対処方法は、症状の捉え方によって変わってきます。
例えば、膝が痛いという方に対して、どこに原因があると予想ができるのかというと
膝、足のおやゆび、足のこゆび、かかと、足くび、くるぶし、ふくらはぎ、太もも、腰、脇腹、肩…と、実はたくさんあります。
じゃあ、そんな数多くあるポイントの取捨選択をどのようにするのか?
そこはそれぞれの先生の考え方によるわけです。
「なぜ、そこを見たんですか?」
「どうして、そこを触れたんですか?」
「どうやって、その場所にアプローチするんですか?」
…という感じで、実際に施術をみながら、細かく質問し、解説をしてもらうというかたちで練習をし合いました。
今まで何度も練習会に参加はしていますが、ここまで理論的に説明をしたり受けたりしながらの練習はなかったので、とても新鮮でした。
特に、ある先生が仰っていた「体重のかかり方を見る」という視点は、今までの自分にはあまりなかったので、大変勉強になりました。

【ペアを組んでの実践組手】
午後の部:多次元操体法練習会
この多次元操体法練習会は、毎月、仙台で上川名 修 先生 が開催されている、多次元操体法講習会に参加したことのある先生の中から、有志が集まって開催されます。

【気持ちよさを味わいながらの調整】
今回のテーマは、今月開催された松島合宿の中で学んだ、触れ方をメインに、いろいろな先生と組みながら、お互いの体の調整をし合いました。
- どこを触れてほしい感覚なのか?
- どこを触れたい感覚なのか?
触れられる側も触れる側も、自分の体の感覚に集中し、ただただ味わうのみ。
面白いことに、ただ触れているだけで、体にはどんどん変化が出てきます。
合宿の中で感じた、受け手と繋がる感覚を、練習を通して再確認することができました。

【膝伸ばし操法の細かいポイントを教えてもらいました】
まとめ
・・・ということで、
午前の練習会では理論的な操体法を学び、午後の練習会では感覚的な操体法を学んできました。
文字でみると、一見、真逆のことを学んできたようなのですが、実は、操体法では、この2つのバランスがとても大切です。
理論を学ぶ中にも感覚の大切さがあり、感覚を感じる中にも、理論の理解が必要です。
自転車の両輪と同じで、この2つのバランスがとれたときに、施術でも大きな効果となって表れるのです。
理論x感覚。
今回のような練習会や講習会を通して、確認をしながら、これからも両輪を磨いて参ります★

【練習会の後に忘年会!1年間お世話になりました♪】